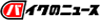クルマ(4輪車)ではほとんど意識しなくて済むことでも、バイクの運転では事故につながることがあります。その代表例が「マンホール上の通過」です。交差点付近やカーブで、バイクの軌跡に立ちふさがるように存在するマンホールは、バイクだからこそ気を付けらなければならない「運転の知恵」が転倒を防ぎます。
「マンホール蓋」の上は、滑りやすい
マンホールは、その名の通りメンテナンスを行う作業員の点検口として利用されています。ほとんどは道路と平行して埋設され、下水道管のほか電気、通信の立て坑として設置されています。下水道管のマンホールは約30m間隔で設置するのが標準的とされ、例えば、東京都内には約48万5000カ所あると東京都下水道局は公表しています。
路上にマンホールがいくつも密集する交差点を見かけることがありますが、下水道管の場合、道路の地下にも路上と同じように地下の下水道管が交差しているため、水流が方向を変えるときに管路に衝突する水圧を、マンホールから地上に垂直方向に逃がす役割も持っています。豪雨でマンホールから雨水が吹き上げるのは、雨量が多すぎて逃げ場がなくなっているためです。
交差点やカーブでの設置はできるだけ無い方が良いのですが、マンホールの設置は避けられない事情があります。
問題は、マンホールは蓋の素材に主に鋳鉄が使われ、とても滑りやすくなっていることです。スリップは摩擦係数の違いで発生します、バイクは車体を傾けることで曲がるきっかけを作るので、車線中央に設置されたマンホールとは相性が悪く、結果的に危ない思いをすることがあります。
ライダーは滑りやすいマンホールを避けることが理想ですが、都市部での走行で避け続けることはほぼ不可能で、マンホールの上は直進して通過すること、交差点やカーブでは充分な減速を心がけることが必要です。
マンホール付近には、段差ができている
マンホール蓋によるスリップ事故の対策として、より滑りにくいマンホール蓋の開発も行われ、順次更新されています。「耐スリップ性能向上マンホール蓋」と呼ばれるもので、表面に突起加工などを施し、道路舗装の滑り抵抗も参考にして抵抗値を向上させています。東京都下水道局が2017年から3年をかけて開発し、2021年から実装され、バイク通過時の走行安定性も確保されつつあります。
ただ、こうした安全対策が進むにつれて、マンホールの上も通過しても大丈夫ではないか、という認識が広がることは運転にとって良いこととは限りません。
もうひとつ、ライダーが気を付けなければならないのは、マンホール付近には段差ができることがある、ということです。
マンホール上での転倒につながりやすい原因は、路面とマンホールとの段差でバイクの操縦が不安定になってしまうことです。
マンホールは通過車両の車重や振動などで劣化するため、更新が必要です。通行規制をできるだけ短期間にするため、取り換えの工法の工夫が行われています。
マンホールの周りをドーナツ状に、必要最小限だけくり抜くように掘削して鋳鉄製のマンホール枠を取り替えるものです。原因は特定できませんが、このドーナツ状の補修部分に段差ができることがあります。
段差は数cmほどなので、ある程度のスピードで前輪と後輪が一直線上にある、つまり正しく直進してマンホールを乗り越える場合には問題は起きません。
ただ、何らかの理由で進路を変えようとして車体を傾けている場合、その段差で前輪が跳ね上がり、さらにマンホールの低い滑り抵抗が手伝って転倒につながることがあります。
この一例は、「軽装はヤバい!」(2024年8月8日配信)の記事の中で事故体験談を紹介しました。ライダーは大型バイクでしたが、小径タイヤやサスペンションのない一般原付以下の車両でも注意が必要です。
東京都下水道局に話を聞きました。
「マンホールの直径は、約90〜150cmほど。地中に下がるほど広がる構造で、(立て坑は道路と並行に埋められた)下水道とつながるので沈下しにくい。一方、アスファルトは地表温度や車重で轍ができることもあり変形しやすい。路面がへこんでもマンホールが沈下しないので段差ができるのかもしれない。しかし、道路に段差があることはあってはいけないので、もし、そうした場所をみつけたら、まずは道路管理者に通報してほしい」(管路管理課)
都道では、道路通報システム「My City Report」(MCR)でデジタル通報できます。国道の場合は道路緊急ダイヤル(#9910)や道路通報システム(MCR)があります。そのほか道府県でも緊急通報ダイヤルが設置されています。
管路管理課の解説の通り、マンホール付近の段差は、前述のようなケースばかりではありません。地盤全体が沈むとマンホールだけが飛び出しているような段差になることもあります。
そうした場所で条件が重なると、大多数には安全であっても転倒につながるケースがあります。快適に走ることができる舗装道でも、潜在するリスクについて考える必要があります。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
弊社ではこの記事で挙げられている円形マンホール蓋取替(GMラウンド工法)と高耐久・長寿命化滑り止め(SR工法)の施工を行っております。
滑り転倒事故には施設管理者も利用者の方々も充分ご注意を!
テック・グランドアップ 防滑施工事業のご紹介ページです。
倒事故撲滅!!防滑施工の重要性
弊社ホームページ https://www.t-ground.co.jp/